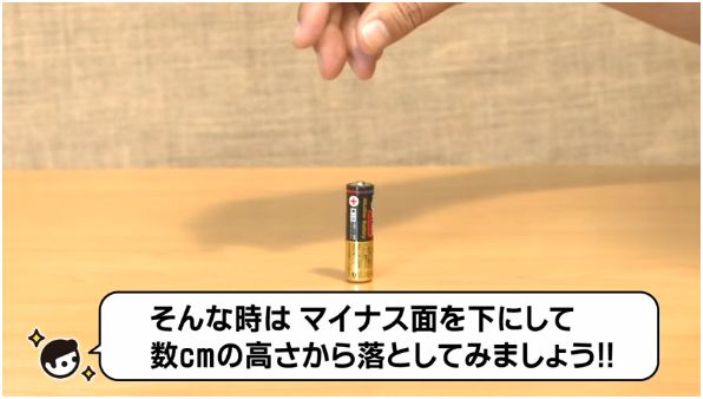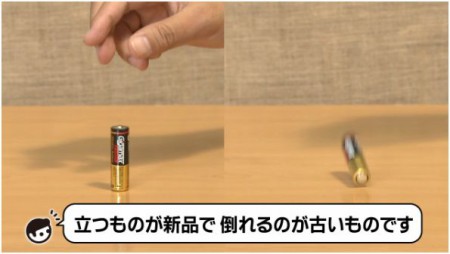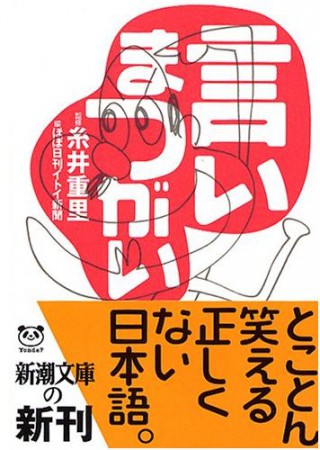マラソン大会初参加!
普段周りの人よりも動いていないのに。
無謀すぎる。
『デザートマラソン』という企画のラフなマラソン大会。
走行距離も10km。
給水ポイントでデザートが食べ放題という
甘い誘惑にものせられて。
お手軽に楽しめる企画だなと、
なまった体をよそに参加してみることに。
初秋とはいえ、炎天下な快晴。
こういうときに晴れ男は困る!?
定期的に運動していたのなんて、
かれこれ1年半-2年近く前のお話。
お話にならない。
たかだか10km、
ハーフマラソンにも満たないとはいえ、
普段まったく運動していないうえに、
参加が決まってからも1回も軽くも走っていない。
不安すぎる。
「暑い」「キツイ」と走りながら、この言葉だけが、
反復してぐるぐる頭のなかを回る。
たいしたラインナップではなかったけれど、
給水ポイントのデザートなんて食べる余裕もない。
いや、食べたらもっと走れなくなる、と確信できる。
歩きも相当加えながら・・・・なんとかゴール。
終わってみれば、楽しかった。
街のなかの大きな公園。
子どもからご年配までたくさんのランナーがいた。
対象ごとにいろんなコース企画が同時並行で実施。
公園も広く、ちょっとしたひなたぼっこ&行楽気分。
今流行りの「B1グルメグランプリ」の
会場になったりするような街の広場。
マラソン大会でもたくさんの出店たちで賑わっていた。
ケバブ・・・ケバブ・・・あまりの行列に断念。
デザートがあまり食べられなかった分、
マラソン後はビールでエネルギー・チャージ!
快晴な空の下、芝生で飲むビールは最高っ!
『1年に1回なにか新しいことにチャレンジしよう』
そう数年前から決めている。
年齢を重ねるごとに、これまでの人生でやったことのない、
初体験なことをしよう、と。
新しい趣味や新しい旅行先などもいいかもしれない。
とにかく今まで経験したことがない◯◯をひとつ、
自分の人生の1ページに加える。
ただ歳を重ねるだけなんてシャク!
どうせ歳とるなら経験もひとつ重ねようゼ!
そんな感じ。
それで30代デビューしたことも結構ある。
そのときは照れや恥ずかしさもあるけれど、
あと10くらい歳を重ねたときに振り返れば、
きっと『あの時やっといてよかった』と笑って思える。
そういう経験をこれからもひとつひとつと、
増やしていきたい。
先々、『あの時こんなことやったね』と笑って言い合える、
そういう人たちがいることに感謝して。
これからも巻き込まれながら、巻き込みながら。