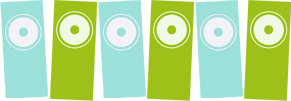もしまだ今年の目標や楽しみが定まってない人。
なにか新しいことをはじめたいと思っている人。
今までとは違う変化や成長を望んでいる人。
それは仕事や趣味など、すべての日常生活において。
以下、本著からの抜粋でひっかかるものがあれば
ぜひ読んでもらいたい一冊。
自分の「大好きなこと」はなにか。
それがわかるだけでも大きな一歩だと思います。
一年のはじまりに出会えてよかった本です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「大好きなことをやらない」6つの理由
1.時間がないと感じている
2.好きなことをやっていいという許可が自分におりていない
3.好きなことでは生活が成り立たないと思っている
4.才能がないと思っている
5.お金がないからできない
6.そもそも好きなことがなにかわからない
「大好きなこと」の7つの側面
1.やっているだけで楽しくなること
2.まわりを楽しませ、幸せな気分にさせること
3.自然とやってしまうようなこと
4.生まれ変わってもやりたいこと
5.お金を払ってでもやりたいこと
6.いつも周りにほめられたり、もっとやったらと薦められること
7.少しでも時間があればやってしまうこと
人生はあなたが生きたいようになる!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~