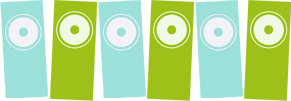さて、目の前に大きな壁が立ちふさがった。
「ピンチは最大のチャンス」
そんな心に染みついている名言が頭をよぎる。
ピンチのときに、
それをチャンスなんて思えない。
そんな呑気な、悠長なこと言ってられない。
たしかに実際にそのピンチに出くわすと、
なかなかそう思える余裕がなくなる。
でも、
チャンスとは、すなわち”転機”ということ。
問題や障害が発生し、
一旦立ち止まり、
来た道を振り返り、
現在地点を俯瞰的に直視しなおし、
そして進む道を定めなおす。
つまり”分岐点” ”岐路”になる地点にいる。
ターニングポイント、
起こったピンチが転機のきっかけとなる。
まさにそうなだと思う。
いろいろなことが思い描いたように
順風満帆にいくならばそれはそれで望ましい。
ただイメージとおりにいかないのが常。
外的要因や想定外の出来事、
もしくは予期していたリスクがついに顔を出す。
人生、障害物競争なのだ。
だから
「ピンチは最大のチャンス」と思えるかどうかは
その先へも影響を及ぼすとても大切な思考法。
マイナスに捉えるか
プラスに捉えるか。
これまたすごく大切。
起こったことは、ただの事象であり事実であり、
それはプラスもマイナスもない、フラットなこと。
そこに人の感情が入ることで、
プラスな出来事にも、マイナスな出来事にも、
なってしまう。
つまり事実をわん曲しているのが
人の思考ということなる。
わかりやすい例でいうと、
【風邪をひいた】は事実でしかなく、
『風邪をひいて寝たきりでムダな数日だった』(マイナス)
『風邪をひいて看病をしてくれる家族の大切さがわかった数日だった』(プラス)
ここまで大きく解釈は人によってかわる。
さらには、
マイナス思考で捉えた前者と、
プラス思考で捉えた後者の、
完治して以降の考えや行動も、
どう変化していくのか、誰しも想像できる。
もっと現在だけでなく、未来形でいうと、
◯◯が起こったことで、後に☓☓になった。(マイナス)
◯◯が起こったことで、後に☆☆になった。(プラス)
未来が☓☓(マイナス)になった人は、
過去の◯◯をもマイナスとする。
未来が☆☆(プラス)になった人は、
過去の◯◯をもプラスとする。
◯◯はただの起こった事だったのだけれど、
未来からは過去の意味さえも変えてしまう。
プラスにもマイナスにも。
事実は事実であり、
起こったことは起こったことであり。
それを冷静に受けとめ、
客観的に分析、原因を突き止めることは必要。
そしてそこからは、
プラス思考で考えたほうが、
一言で言ってしまえば”得”だと思う。
マイナス思考でいい解決策が導き出せるとも思えない。
ポジティブ思考とはビジネスの世界だけではなく、
人生そのものに対してポジティブ・シンキングのすすめ。
ロールプレイングゲームでもそう。
敵に遭遇して、
「あれ、オレこんな武器も持ってたんだ!」
「意外にもいい装備してたんだな!」
「一緒に戦う、助けてくれる仲間がいるじゃないか!」
「戦いのなかで新しい戦い方や知恵を学んだな!」
「こんな戦い方もあったんだ、次は楽勝!」
そして敵を倒して、アイテム手に入れたり、
レベルアップしたり、さらにフィールドを進んでいく。
置き換えたらRPGそのまんまだな、とも思う。
そう、だから、
『ピンチは最大のチャンス』 = 転機が訪れた
起こった事実をリアル(現実的)に捉え、
楽観的にプラス思考で解決策を模索する。
現実と楽観のあいだ
Be Cool , Be Positive!
なのである。