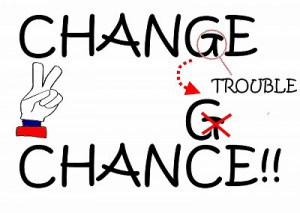以前にも触れたことのあるこの言葉、『すでに起こった未来』。
P.F.ドラッカーの同名著書の日本語題です。
昔読んだ本なので、内容の記憶はほとんど残ってなく・・。
世界経済論だったと思います大枠で。
政治・経済・社会・企業のトレンドについて、
激動と大転換の現代とその本質を知るためには、みたいな。
本の内容はうっすらながら、それでもこの言葉は強烈に残っています。
『すでに起こった未来』
いい響きです。
同時にすごく違和感があるからこそインパクトのある言葉。
なんで未来なのに“起こった”という過去形?
そこにこの言葉の核があるんですね。
過去は繰り返す、時代は繰り返す、なんて言葉がありますよね。
今起きてることはこの先にも起こり得る、こういう言葉もありますね。
言ってしまえば、そういうことなんです。
未来を創るため変えるためには、
また、動いている現在を捉えるためには、
過去から学ぶこと、今を本質的に知ること、
その普遍性を掴むことが大切。
仕事でもそうですよね。
今起きている問題は、過去にはなかったのか?
今起きている問題は、未来にどういう影響を及ぼすか?
例えば、それが初めての課題や問題かもしれません。
でもそれは「あなたにとって」であり、
「あなたがいる環境」に限定されたものです。
他人・他社・異業種など環境を広げて見渡してみたら、
同じような問題はないのか。
ということは。
あなたが今抱えている未来に起こり得る問題は、
違う場所では『すでに起こった過去』=過去の事実・現象 であり
今のあなたにとっての『すでに起こった未来』=未来の投影 となるわけです。
現象を
その時特有の状況(当事者・トレンド・流行)で狭く偏って捉えずに
俯瞰的・普遍的・客観的に本質を見抜く、その思考です。
深いですよね。
仕事だけじゃないです。
毎日の中でのいろいろな問題にも共通していることだと思います。
『すでに起こった未来』を自分の眼で確かめることで、
過去や現在から学んだそれは、全く同じことを繰り返さずに済む可能性があります。
ちょっとこんがらがってきますね。
要するに、
『すでに起こった未来』を自分のものにすることで、
『これから起こる未来』を新しく創っていける。
まさにこれが言いたかったのです。
妙に哲学的なくだりになってしまいました。
それだけとてもインパクトのある言葉であり、
印象的でずっと頭から離れない、
自分にとっては大きななにかを持っている言葉です。
ちなみに。
『すでに起こった未来 -変化を読む眼-』 P.F.ドラッカー
この書籍の原題は、
“THE ECOLOGICAL VISION – Reflections on the American Condition”
(社会生態学的な見通し―アメリカの条件を振り返る)
本の内容はこの原題そのものというわけですが、
この本の日本語タイトル考えた人、キャッチコピーの爆発力すごい。
ドラッカーは世界中で翻訳され
多くの人に読まれていまる名著がたくさんありますが、
そういえば・・・どの日本語題もセンスやインパクトがある。
このあたりの角度から「現代広告やキャッチフレーズ」なんかを
考察してみるのもおもしろいかもしれませんね。
脱線しました。
何か問題に直面したときには、
『これは “すでに起こった未来” 、必ず解決策はある!道は開ける!』
そういう気持ちで臨んでいこうと思います。