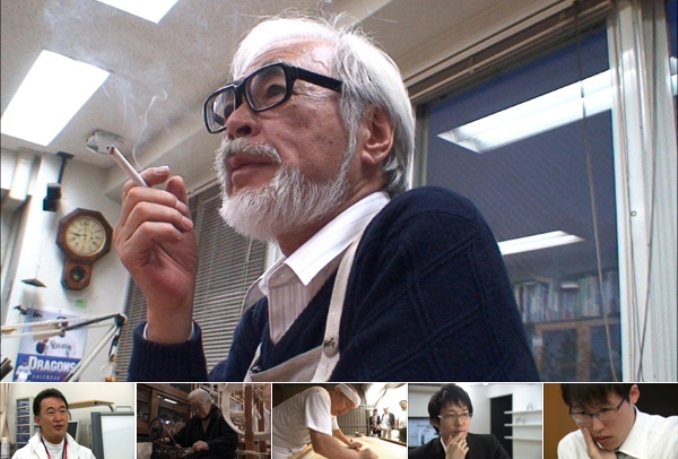結果を出せなかったときにどう受け止めるか。
これがカギになってくる。
・たまたま負けたと運のせいにする
・~~が悪いと責任転嫁する
・相手が強かっただけと諦める
・自分も年をとったと頭を抱える
ではなくて、
事実をどう受け止めて分析するか。
そしてひとつひとつ問題を改善・解決していく。
安易で楽な方法で結果を出すよりも
地道で遠回りな継続でしか手に入れることのできない強さ
というのがある。
結果を出し続けるということは、
その継続のなかに成長・変化がありそのスパイラルアップで
勝ち続ける力へと進化していく。
『急がば回れ』
ここには本当に大切な教訓がある。
即席で身につけた能力や知識なんてすぐに使えなくなります。
瞬間的にしか効果も発揮しなければ、すぐに通用しなくなります。
見方を変えれば、
それは他の人もすぐに身につけれてしまう程度のもの
ということにもなります。
それよりも瞬間的な結果や瞬間的な勝ち負けに一喜一憂せずに
正しい目標と、正しい期間設定と、正しいやり方で、
継続して努力していくほうが磨いていくほうがきっと将来輝きます。
ビジネスの世界でもスポーツの世界でも、
だから結果を出し続けている会社、選手ってその凄みが違うんです。
そこにはどんな決定的な差があるのか?
自分が思うに、仮に10年後も20年後も
『戦い続ける・向き合い続ける覚悟があるか?』
そしてどんな失敗や挫折があっても屈しない
『自分をどれだけ信じられるか?』
このふたつが「勝ち続けるため」の志 という結論。 2013.秋 現在