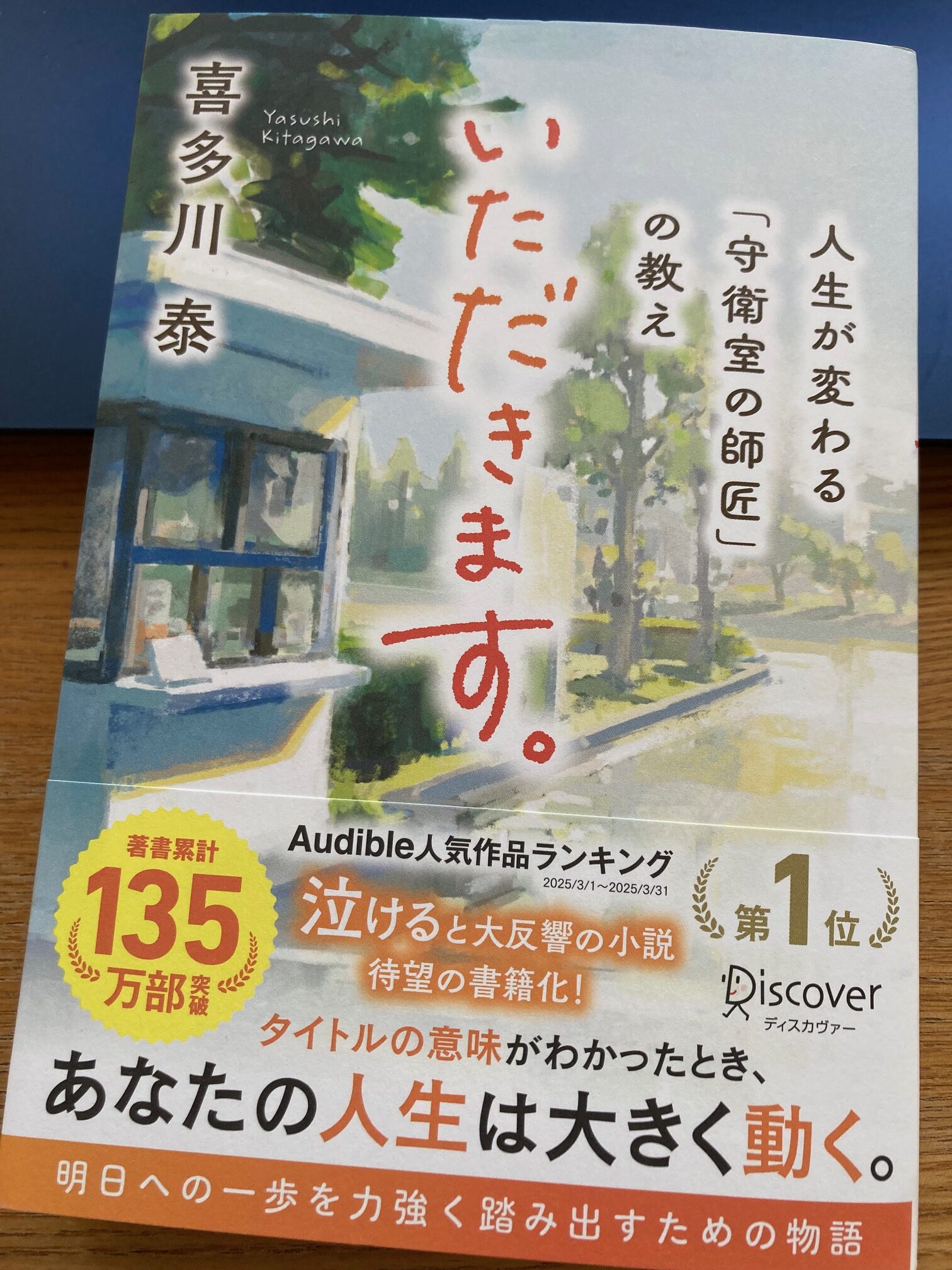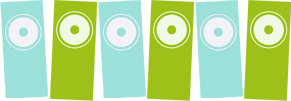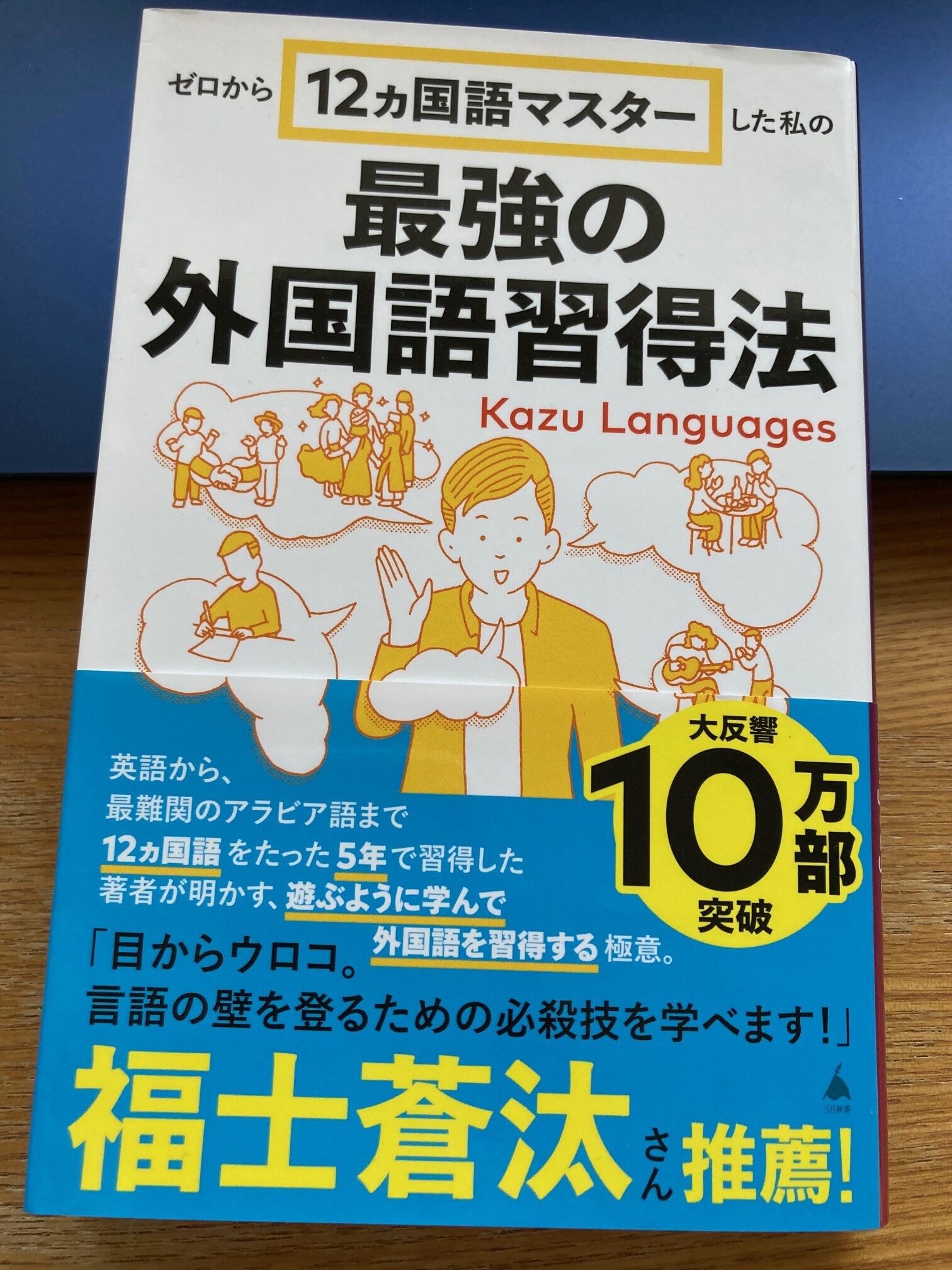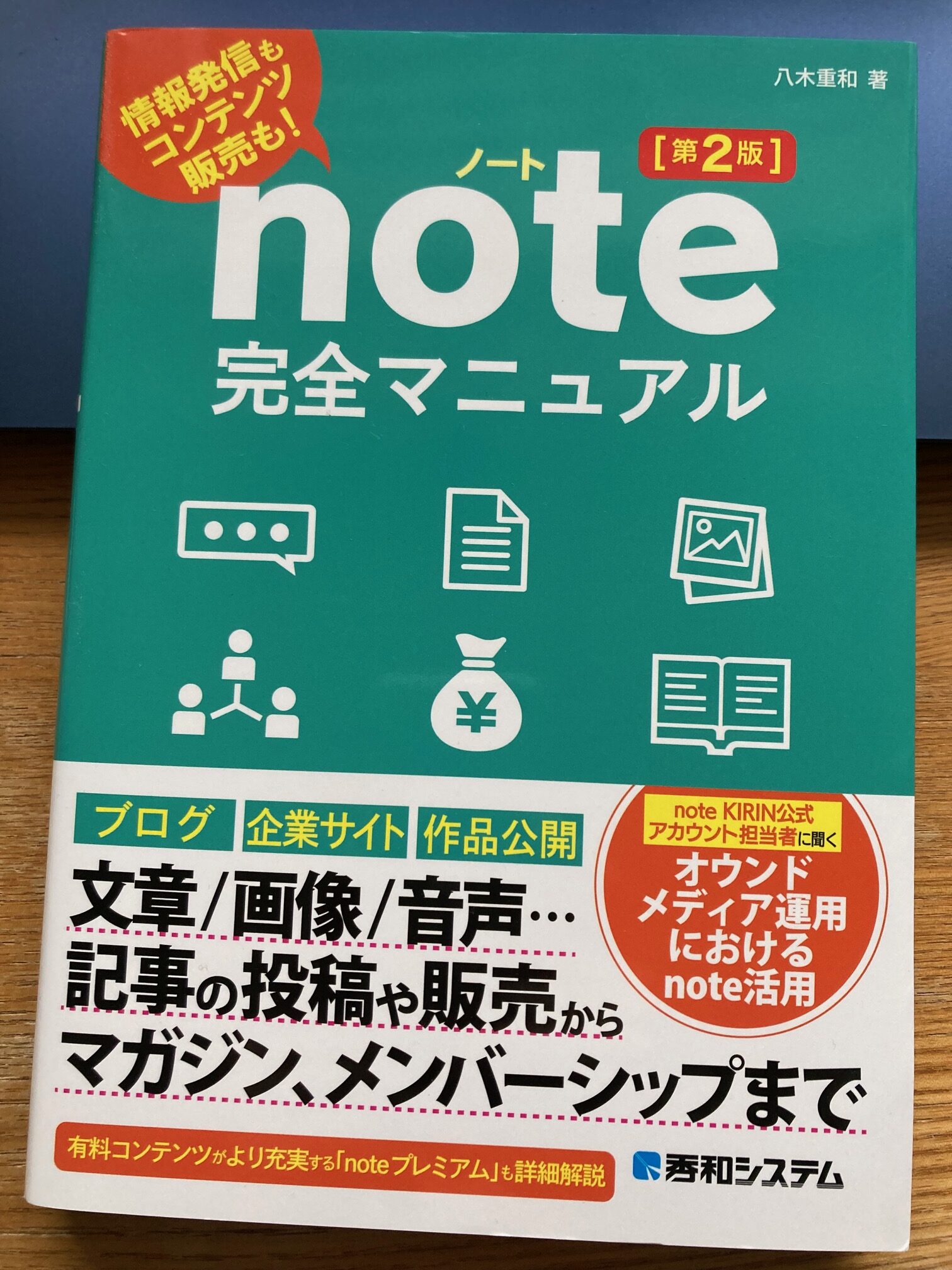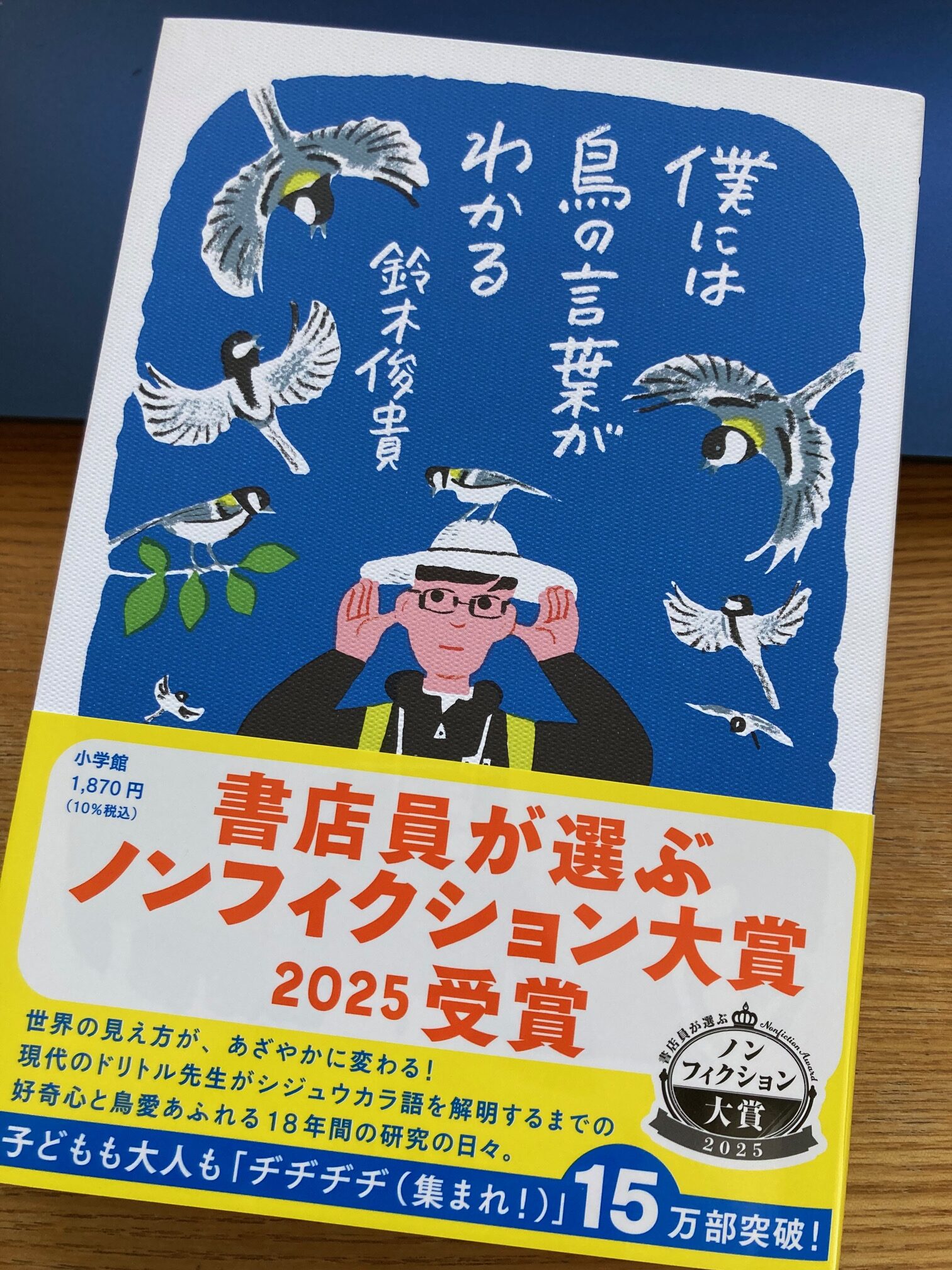「いただきます。 人生が変わる「守衛室の師匠」の教え」
この人の本はよく読んでいる。
ふと本屋に立ち寄ったら見つけた最新刊。
シンプルなことを言ってるんだけを
考え方が変わったり深くなったりする。
ストーリーよりも登場人物たちに何を語らせるか。
それをいつも楽しみにしている著者。
印象に残ったセリフから一つ。
「だって、誰でもできる仕事が一番、誰がやるかで差が出るからさ」
「そう。誰でもできることをやらせたときに、誰にもできないところまでやる人がいるとするよね。そこにできる差のことを『その人にしかできないこと』って呼んでるんだよ。実際その部分は誰にもできないわけでしょ」