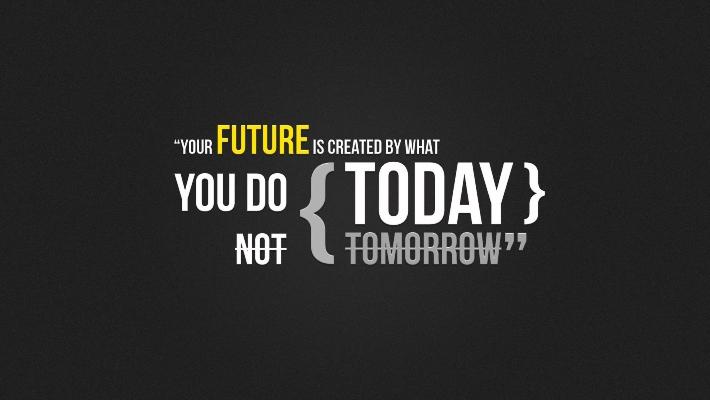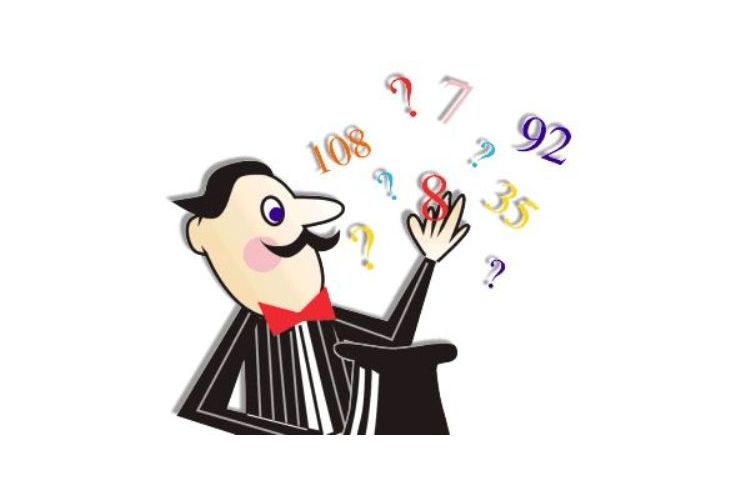日常生活のなかで
突然不安に襲われることは誰しもある。
今やっていることへの不安。
これからどうなるかへの不安。
やりたいと思っていること
やらなければいけないこと
いまだにやれていない
いまだに手を付けれていない
いまだに到達レベルにいけていない
仕事でもプライベートでも。
不安や焦りだけがつのる瞬間。
動いていないゆえに起こる不安ならば
そこはまず動くしかない。
動き出すことで不安は解消され
モヤモヤが晴れることはたくさんある。
動いている最中で、行く先への不安。
これが厄介だ。
ひとつの考え方に、
「3年後や5年後という長期スパンで見据える」
今できていなくても、
3-5年後にはできている可能性は十分にある。
それだけ時間をかけた継続的努力を
つづけることができれば。
3年後、5年後の未来イメージから逆算で
目標や計画を立てる。
そこへ向けて進みつづける。
噛み砕いていえば、
今できていなくても3-5年後クリアしていれば
御の字じゃないか!という楽観的プラス思考。
達成したい思いはわかるので、
いつまでに? というところが大切なことろ。
その不安は今すぐに解消されたいのか?
5年後に解消されていればOKなのか?
どの時点でマルとなっていれば自分が満たされるのか
もう一度深呼吸して考えてみる。
すると、今怒涛のように押し寄せる不安たちが、
穏やかに静まることもある。
5年後に笑っていられるならいいじゃないか、と。
ひとつの考え方に、
「1年後という少し先のスパンで見据える」
3年後や5年後だとイメージしずらいこともある。
1年後であれば、もう少し具体的にできる。
実現可能性のある目標や計画、達成イメージ。
それを毎年くり返して、3-5回積み重ねる。
するとおのずと3年後、5年後にある。
デメリットとしては、
3-5年後という長期スパンではないため
飛躍的な目標や発想がしずらい。
どうしても現実味をおびたものになる。
逆にメリットとしては、
地に足がついた目標ということになる。
突飛なものではないので、
それだけ達成確率も高くなってくる。
また5年後のことなら「5年の間にいつか」など
悠長に構えてしまうところもあるが
1年後なら、「1年間なんてあっという間だから」と
切羽つまって行動をかきたてられる。
1年に1回、
なにかひとつのことを達成、一歩成長することは、
5年後には5つの達成、成長になる。
これは大きい。
ひとつのことを深く掘り下げても5レベルアップ。
それぞれの目標を毎年クリアしても5レベルアップ。
広く、深く、どちらにせよ今よりも5レベルアップ。
要は目標や計画、総じて自己実現欲求を、
どの未来スパンで見据えて、日々臨むかということ。
目標も計画も、なりたい自分も、
緩急をつけて考え行動していかないと、
継続的実践はつづかない。
雲をつかむような、
おぼろげな不安、ふわっとした将来のこと。
そこには、こういった考え方をすることで、
一気に視界が開けることもある。
今考えてもしょうがない不安
今考えても飛び級できない未来
そんな焦りから解放されて、
「さっ、今自分にできることは!」と気持ちを切り替える。
5年後の大きな未来を明るくイメージして、
1年後の手ごたえのある未来へと突き進む。
それを胸に掲げていながら・・・
今日の小さな目標をやらない。
明日の未来がわかっていながら、
手を付けない、先延ばしにしてしまう。
5年後のことなら”want”や”wish”といった
希望的な夢リストでいいけれど、
今日のことや明日のことなら、
それは間違いなく”To Do”リストに置き換わっている。
つまり
“やらなければいけないこと”
”必ずやること”
そこからしか、1年後へ5年後の変化は生まれない。
だから今日も精一杯がんばる!