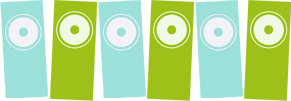プロ野球監督としても有名な野村克也さんの著書です。
野球人生で培われた教訓や人生における名言が紹介されています。
人の言葉ではなく、自らの経験からくる自分の言葉として。
スポーツをする人、多くのビジネスマン、30代以降の中間管理職まで、
戦う人、上司や部下の環境の人、自らを高めたい人、
見開きで1項目という読みやすさで99の名言が胸を打ちます。
「弱者」という副題がついていますが、
これは野村監督のこれまでの歩みが反映されていますね。
無名高校からテスト入団し、捕手として打者として頂点を極め、
監督としても万年Bクラスのチームを常勝軍団に育て上げた背景が。
だからこそ、
・弱者はいかに闘い、いかに勝つべきか
・現実をどう認識し、戦略を練るかですべては決まる
・人間の能力や才能の差など、ほんの僅かにすぎない
といった、
一握りの天才ではなく、人はその意識と鍛錬で変われる!ということを
経験から紐づくエピソードと言葉で語られていますので、
とても勇気づけられます。
目次から紹介しますと
- 不器用は最後に器用に勝る
- 才能のない者の武器は考えること
- 勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし
- 自分は毎日正しい努力をしているか、毎日自分に問いかけよ
- 時間は平等に与えられるが、結果は平等ではない
- 未熟者にスランプなし
- 満足・妥協・限定は負のスパイラル
- プロフェッショナルの”プロ”はプロセスの”プロ”
- 忍耐の裏にあるのは希望である
- 組織はリーダーの力量以上には伸びない
- 覚悟に勝る決断なし
- 人間はどんなときにも手を抜いてはいけない
- どこで誰が評価してくれているかわからない
- 人間は無視・称賛・非難の順で試される
- 進歩とは無知を自覚することからはじまる
- 人間的成長なくして技術的進歩なし
- 才能とは頭脳に埋め込まれた情報である
- 若いときに流さなかった汗は、年老いて涙に変わる
- ぼやきと愚痴は違う
- 進むときは上を向いて進め。暮らすときは下を向いて暮らせ。 etc
もちろん野球に関することも多いですが、
上に抜粋したように、その枠にとどまらない人生訓がたくさんあります。
一番突き刺さった言葉は、
『若いときに流さなかった汗は、年老いて涙に変わる』 です。
カッコイイー!
いやそういうことではないんですが、肝に銘じたいと思いましたね。
あとは、
不器用な人は要領が悪く、失敗を繰り返し時間がかかる。
だからこそ、努力を積み重ね、試行錯誤し、創意工夫し、
知識や理論、経験則が蓄積されていく。
一度身についたものは失われない。だから器用になる必要はない。
このあたりの話も、とても背中を押してくれる言葉だと思います。