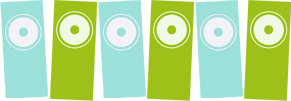保険を見なおした。自分にかける保険を。
こう書き出すと、ちょっとこわい。
この度友人の保険にお世話になることにした。
プランを決めるにあたって、改めて保険の詳細を知った、というくらい
全然無知だったし、普段あまり気にとめることもなかった。
自分が今契約している保険の内容すら把握していなかったくらい。
保険とは、まさに「もしもの時に備えて」なのだが、
そのもしも、をあまり想定しない。
「自分は大丈夫。自分には起こらない。起こる確率は低いし。。」
と思ってしまう。
友人に言われた。
『保険はお守りと思ってください』と。
そうだ、そのとおりだ。
掛け捨てとか元が取れない、とかそういうことではないのだ。
何が起こっても自分で誰にも迷惑をかけずに乗りきれる人は、
そうしたらいい。
でも、何かが起こって自分自身が、大切な人が、困りはしないか。
今回いろんな説明をしっかり聞いて、納得のいく契約ができた。
それ以上に思うこと。
『信頼できる人に、自分の今と将来を預けている安心感』。
なにかないかいつも気にとめてくれる。
なにかが起こったときには強い味方、支えになってくれる。
自分の生活環境や人生プランに対して、その都度適切なアドバイスをくれる。
こんなに心強いことはない。
保険に入ったほうがいいとか、そういう話ではなく。
まずは自分の身は自分で守ろうとしてみる、考えてみること。
自分の未来への保険は、自分で考え、今どうしておくべきか決断すること。
自分自身を守れないと、大切な人、家族のことなんて、守れない。
そんな教訓が学べた機会になった。
保険の契約をとおして、今の保険業界や医療業界の話なんかもかじれて
なるほどー、と聞く話すべてが新鮮。
やはり友人もその道のプロ。
おみそれしました。
そんなSくん、誕生日おめでとう!