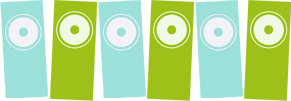First Mover Advantageという言葉がある。
最初に動いた者が優位、つまり先行者利益のようなもの。
先行者利益とは、市場開拓者であり、
パイ(市場・需要)を独占しているので、それだけ恩恵も大きい。
そしてそこに参入しようとすると、後発は簡単ではない。
構築されたパイを崩す・奪い合う、という競争になる。
まあ簡単に言えば、
後発は不利だし、そう簡単には勝てない、切り崩せない。
そこで楽天社長の三木谷浩史さんの言葉。
「簡単に勝とうとするから、勝てないだけのことだ。
大きな戦略を描いて、時間をかければ、大概のものは逆転できる。
First Moverになれなかったら、Best Moverになればいい。」
こういうことだと思う。
つまり、First Mover(先行者)になれない場合
・自分がはじめてもすでに勝ち目はない
・もう誰かやってるし自分はやらない
ではなくて、
Best Mover(最善者)になればいい。
・大きな視点か長期的に見て計画行動する
・簡単に結果を出そうとせずに、未来の結果に焦点を当てる
・広く浅くつまむのではなく、ひとつのことを正しいやり方で深く探究する
そうすることで、誰でも、
Best Mover Advantageを勝ち取ることができる。
だから、仕事でも趣味でもなんでもそう。
Never too late.
遅すぎるということはない。
自分が今だ!と思った
BestなタイミングにBestな動きを始めてみたらいい。
すると将来BestなAdvantageを得ている自分に出会うことができる。
Best Mover Advantage だから!! Never too late.
このふたつのセンテンスは合わせて覚えるとより深みが増します。