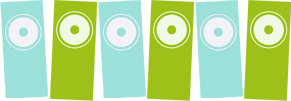クレドとは、企業理念とか行動指針という意味。
どの会社でも同じようなものは必ずあると思うし
それが会社に飾られていたり、社員に配られたり、手帳にあったり。
その個人版。
自分の好きな言葉 モットー 軸 肝に銘じたいこと こうありたいこと
ふとしたときの頭の整理やストレッチのために。
そして1日1回は、これを眺めるようにしている。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【 2013年 クレド 】
0.本当の旅とは、新しい土地を探すことではなく、新しい目で見ること
1.至誠天に通ず
2.仕事と思うな、人生と思え
3.Path Finding ~道なき道をみつける~
4.自分と未来は、変えることができる
5.タイミング・イズ・マネー 今がその時
6.No Challenge , No Future
7.アウトプットを想定したインプット 経験値と創造力
8.マトリックス二軸で考える。深く。広く。
9.発想展開力 ~what if 置き換え SCAMPER オズボーン
10.G+PDCA+S
11.Being , Having , Doing
12.敵は誰ですか?私です。
13.1日1回「思考」と「改善」 self talk diary
14.3年後の自分は、今日の自分を褒めてくれますか?
15.才能の差はない。行動の差は大きい。継続の差はもっと大きい。
16.never too late. 遅すぎるということはない。
17.いまこの瞬間から始めれば、なんでもできる。不可能はない。
18.今週の点数は? 今週をひと言で言うと?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
難しい専門用語もあるので、なにかの機会に触れることができたら。
そして来年はもっと進化したクレドに改訂できるよう今年進みつづける。